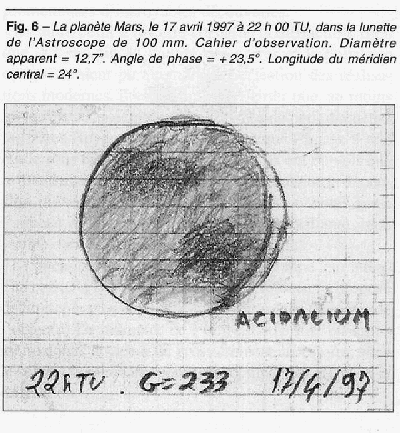96/97 Mars Sketch (13)
1996/97 Mars Sketch (13) - from CMO #210
** ホイヘンス對ドルフュス **
 ★今回は異例だが、SAF(la Societe Astronomique de France)のA4判機關誌l'Astronomieの1998年四-五月號から、ドルフュス(Audouin DOLLFUS)氏の 17 April 1997の火星のスケッチを引用・紹介する。この圖はホイヘンス型の筒なし望遠鏡によるスケッチで、歴史的な意味で興味深いものである。
★今回は異例だが、SAF(la Societe Astronomique de France)のA4判機關誌l'Astronomieの1998年四-五月號から、ドルフュス(Audouin DOLLFUS)氏の 17 April 1997の火星のスケッチを引用・紹介する。この圖はホイヘンス型の筒なし望遠鏡によるスケッチで、歴史的な意味で興味深いものである。
★1995年四月のSAFの會議で、ホイヘンス(Christiaan HUYGENS 1629 - 1695)の筒なし望遠鏡(Astroscope)の歴史的復元は、文化的、科學的、教育的見地からも意味があろうという話になった様で、多くの人が參加して實際に作り上げたようである。A DOLLFUS氏の他、P BACCHUS、F BIRAUD、R BOTTARD、B DAVERSIN、G FARRONI、J FORT,、J-M LECLEIRE、 P MOATHY、 G PHILIPPON、A THIOT氏などの名が見える。實は、先の號はホイヘンス一色の特集號で、さまざまな話題が取り纏められており、DOLLFUS氏は實作記事の他、ホイヘンス兄弟や筒なし望遠鏡の話など書いている。
(Fig 1) From the rear cover of l'Astronomie avril-mai 1998
 ★ここで作られた望遠鏡は先ずポール(マスト)があって、そのポールに沿って上下できる形で、対物レンズが取り付けられており、これが離れて置かれたマウントと接眼部に、筒でなく紐で繋がっているという類のものである(Fig 1)。対物鏡は弥次郎兵衛でバランスが取られていて、紐を張れば接眼部の方に向くというものだが、一旦星が入っても、すぐに日周運動で出て行くであろうから、大変である。實際にはホイヘンスは菱を工夫している様で、引用の菱は、その設計圖で(Fig 2)、これにはDessin A DとあるからDOLLFUS氏の描いたものであろう。足を持って微妙に調整して行くようである。
★ここで作られた望遠鏡は先ずポール(マスト)があって、そのポールに沿って上下できる形で、対物レンズが取り付けられており、これが離れて置かれたマウントと接眼部に、筒でなく紐で繋がっているという類のものである(Fig 1)。対物鏡は弥次郎兵衛でバランスが取られていて、紐を張れば接眼部の方に向くというものだが、一旦星が入っても、すぐに日周運動で出て行くであろうから、大変である。實際にはホイヘンスは菱を工夫している様で、引用の菱は、その設計圖で(Fig 2)、これにはDessin A DとあるからDOLLFUS氏の描いたものであろう。足を持って微妙に調整して行くようである。
★紐は楽器の弦の締め方で締めたり、光軸合わせ等、本當はローソクを使ったりしたそうだが、少なくとも助っ人が二人は必要で、その他、實際には風の影響など難しい事がある様である。
★対物鏡は單レンズで、LECLEIRE氏が研いた。本來のホイヘンスの物は口徑4.6プース=11.6cmとなっているようだが、この工作では13cm、焦點距離は本來は34ピエ=10.5mなのだそうだが、このレンズは7mの由。接眼鏡も工作していて、91.5mmの焦點距離、直徑は89mmだそうだから、大型である。これで76倍が得られる。實際にDOLLFUS氏の記述では、口徑10cmとなっているし、倍率もPlosslを使って變えている様で、引用の火星の場合233倍とあるから、もっと短い焦點距離のアイピースを使っている。
★対物鏡の焦點距離が7mもあるから、ポールは8mは必要で、その周りを巡るわけだから、可成りのスペースが要る。設置場所はTriel-sur-Seine(パリの西,Yvelines県、同じ県にOgerさんは住んでいる)のTriel天文臺の“星の公園”というところを選んだ様で、觀光としても意味があったのか、市役所や市長さんも動員されているようである。1996年十月12日の偏日食のときは300人が集まったそうである。投影方式で見せている。
(Fig 2) Lozenge a la HUYGENS designed by Prof DOLLFUS
★さて、Mars Sketchであるが、これはDOLLFUS氏の二重星(αHerculis)や木星やHB彗星などの觀察の一環で、17 Apr 1997 22:00TU(106゚Ls)に取られた(Fig 3)。233×10cm Astroscope。最接近は既に過ぎていて視直徑は12.7秒角、位相角は23.5度になっているが、缺け具合がよく分かるのは流石である。ω=025゚Wで、マレ・アキダリウムが明確に見えている。左の方の影はアウロラエ・シヌスを含む領域のようである(En haut a gauche, une formation plus confuse correspond a la region somble Aurorae Sinus)。季節は106゚Lsだから、從って、北極冠は小さくなっており、これは見えないようである(角度にして2"×1"ほど)。ただ、下方がボンヤリと明るいらしい。
★實は、DOLLFUS氏は100倍でも火星を見ていて、その火星のスケッチと、ピク・デュ・ミディの1m鏡の1000倍でスケッチした視直徑1.2秒角のガニュメデのスケッチと比べている。コントラストを除き暗色模様のボヤボヤ状態はよく似ているわけである。筆者には100倍の火星は相當辛いし、1000倍のガニュメデなど縁がない。
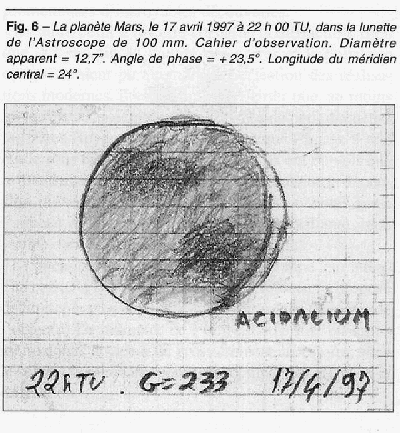

left : (Fig 3) DOLLFUS' Drawing on 17 Apr 1997 at ω=025゚W
right : (Fig 4) HUYGENS' Drawing on 7 Apr 1683
★ここで、1683年のホイヘンスの火星のスケッチを思い出したので挙げておこう(Fig 4)。7 Apr 1683 9.5h (=21.5h)の火星で、36ピエの望遠鏡によっている(但し、筒なし望遠鏡ではない。筒なしは1683年八月以降のアイデアだからである)。ドルフュス氏の今回の火星とよく似ていると思う。テルビィ(F TERBY)の解釋は違うのであるが、『天界』1984年七月號に書いたように、ホイヘンスはマレ・アキダリウムを見ていると思う。
★そこで述べたが、CMO#106p909でも詳説したように、284年というのは非常に好い回歸周期で、1683+284=1967で、ホイヘンスのこの火星は1967年の火星に似ているのである。この年の衝は四月15日で、季節は120゚Lsであったから、北極冠はドルフュス氏の場合より小さく、ホイヘンスの望遠鏡では引っ掛からなかったのであろう。(1997年は1967年の30年後で、30年は必ずしも好い回歸ではないが、似ていないことはない。實は1999年が1983年の79年周期に相當する。∵4×79+1683=1999。來年の衝の季節は129゚Lsである。79年は必ずしも好くない。)
★ドルフュス氏はホイヘンスの南極冠発見が 13 Aug 1672の大接近時であったこと、この時は極冠の大きさが6"もあったことに觸れている。今回は2"足らずであったが、6"あれば、ホイヘンスの望遠鏡でも可能というわけであろう。1672+284=1956であるから、1672年の火星は1956年に回歸しているわけである。1956年には南極冠は小望遠鏡でも明確であった。ドルフュス氏は、ここでも1956年の彼のシュルティス・マイヨル中心のスケッチとホイヘンスの有名な1659年(28 Nov 1659)のシュルティス・マイヨルのスケッチ(CMO#106參照)を並べて、300年でこれだけ進歩したと言う風に申しておいでだが、それはそうだとして、一つだけ注意しておくと、1956年は今述べたように1672年に對應しているのに對し、1659年は1659+284=1943年に對應していて、この時の最接近(29 Nov 1943)の季節が345゚Lsであるから、シュルティス・マイヨルは兎も角、南極冠は消えているのであって、ホイヘンスが1659年に南極冠を描いていないことは當然で、南極冠附きの1956年と比較されるのは少々可哀想である。
★ホイヘンスについて、1988年の『スカイウォッチャー』(九月號か)の火星記事にコラムとして書いたのだが、載せられなかったように思うので、參考の爲最後に當時のFDから写す(圖は略す)。
-------------------------------------------------------------------
ホイヘンスの火星
ホイヘンスは17世紀を代表する科学者で、その業績は数学、天文学、物理学とくに力学、光学といろいろな方面にわたる。なかでも、波動光学での素元波に関する「ホイヘンスの原理」は理科系の人は一度は習うホイヘンスの業績である。
ホイヘンスの天文への寄与は、土星の第一衛星や環の発見、オリオン大星雲やトラペジウムの検出などよく知られているが、火星の表面模様を初めて描いたという点でも有名である。
クリスチアーン・ホイヘンスは1629年にハーグで生まれた。名門だったようで、父はデカルトの知り合いである。デカルトはしばしばホイヘンスの家を訪れて、ホイヘンスの才能を見抜いていたようである。教育は数学と外交官になるための法律を受けるのだが、彼は前者を選ぶ。20代には幾何学から確率論、あるいは力学から幾何光学について書いている。しかし、すでに27歳のころ兄とレンズ磨きに手を染め、望遠鏡を作り、間もなく土星の衛星チタンを見付けるのである(1655年)。同じ頃、振子時計を発明したりしているが、これは70年代の調和振動子の研究に、またフックとの論争に繋がる。
ホイヘンスが火星を見ていたらしいことは、1656年などに痕跡があるが、火星に模様をみつけスケッチするのは1659年11月28日がはじめてである(1図と2図)。ちょうど、こんにち大シュルチスとよばれている大きな暗色模様が中央子午線を通過中で、ヘラスやサバ人の湾あたりまで正確に捉えられている。1図と2図には2時間半の開きがあるが、その間自転で模様が動いているのが判る。二日あとにはもう一度2枚のスケッチをとり、同じように自転を見ている。これらから火星の自転周期が24時間強と知れたわけである。
ホイヘンスの使った望遠鏡についてはよくわからないが、このころは焦点距離で表すならいがあって、1659年の望遠鏡の焦点距離は6.8mほどだったようである。
ホイヘンスは死の前年迄火星をみているが、遺されているスケッチは13枚だけである。1659年の次は1672年のスケッチで、再び大シュルチスがあらわれるほか、南極冠がそれとはっきり描かれている(5図と6図)。ホイヘンスは1670年には重い病気にかかっているが、70年代はホイヘンスの原理を含むかれの波動光学を完成するころにあたっている。
1683年のスケッチは焦点距離11m強の望遠鏡を使っている(ただしまだいわゆる空中望遠鏡ではない)。中央緯度は約南緯20度くらいで、北半球がよくみえている。ただ、模様の同定はなかなか難しい。1876年にテルビがこれらの暗色模様を特定している(スキアパレルリの名称の発表される前年で、プロクター流の古い表記法によっている)。テルビの分類ではアキダリアの海に相当する部分がないが、スケッチをみると、アキダリアの海と言えそうな暗色模様が出ていると思うがどうであろうか。
ホイヘンスの業績は何度かのパリ滞在中になされたものだが、この1683年の観測はハーグだろうと思う。1689年にはイギリスに赴き、少し若いニュートンと会う。1695年何度目かの病気におちいるが、今度は回復しなかった。生涯独身であった。
(1988年臺北にて南記)
-------------------------------------------------------------------
(南 政 次)
 ★ここで作られた望遠鏡は先ずポール(マスト)があって、そのポールに沿って上下できる形で、対物レンズが取り付けられており、これが離れて置かれたマウントと接眼部に、筒でなく紐で繋がっているという類のものである(Fig 1)。対物鏡は弥次郎兵衛でバランスが取られていて、紐を張れば接眼部の方に向くというものだが、一旦星が入っても、すぐに日周運動で出て行くであろうから、大変である。實際にはホイヘンスは菱を工夫している様で、引用の菱は、その設計圖で(Fig 2)、これにはDessin A DとあるからDOLLFUS氏の描いたものであろう。足を持って微妙に調整して行くようである。
★ここで作られた望遠鏡は先ずポール(マスト)があって、そのポールに沿って上下できる形で、対物レンズが取り付けられており、これが離れて置かれたマウントと接眼部に、筒でなく紐で繋がっているという類のものである(Fig 1)。対物鏡は弥次郎兵衛でバランスが取られていて、紐を張れば接眼部の方に向くというものだが、一旦星が入っても、すぐに日周運動で出て行くであろうから、大変である。實際にはホイヘンスは菱を工夫している様で、引用の菱は、その設計圖で(Fig 2)、これにはDessin A DとあるからDOLLFUS氏の描いたものであろう。足を持って微妙に調整して行くようである。 ★今回は異例だが、SAF(la Societe Astronomique de France)のA4判機關誌l'Astronomieの1998年四-五月號から、ドルフュス(Audouin DOLLFUS)氏の 17 April 1997の火星のスケッチを引用・紹介する。この圖はホイヘンス型の筒なし望遠鏡によるスケッチで、歴史的な意味で興味深いものである。
★今回は異例だが、SAF(la Societe Astronomique de France)のA4判機關誌l'Astronomieの1998年四-五月號から、ドルフュス(Audouin DOLLFUS)氏の 17 April 1997の火星のスケッチを引用・紹介する。この圖はホイヘンス型の筒なし望遠鏡によるスケッチで、歴史的な意味で興味深いものである。